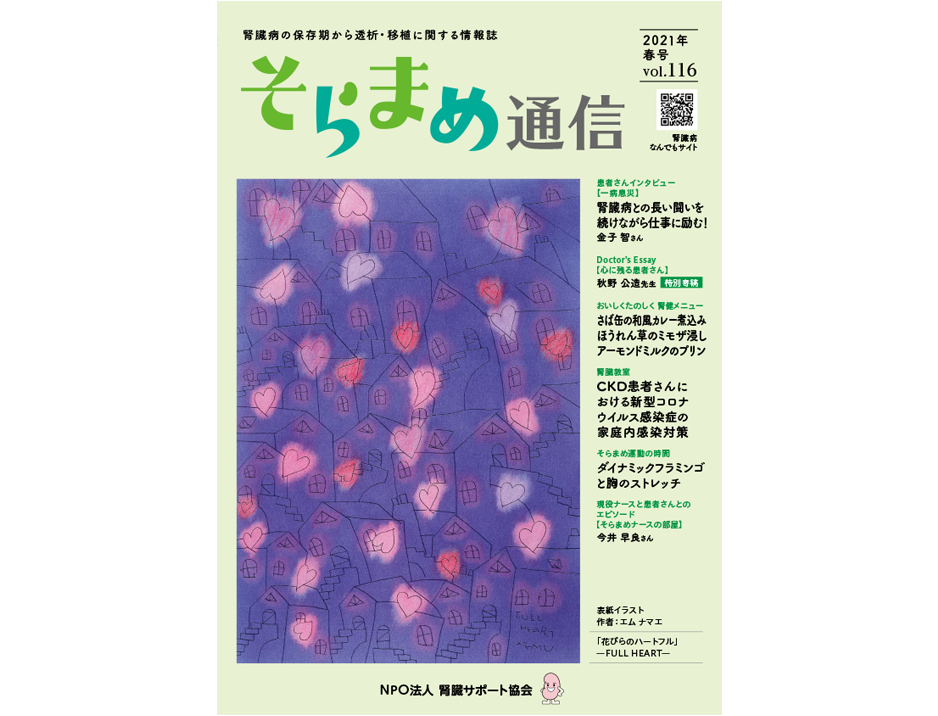最新情報
- 2024年04月15日 そらまめ通信
-
そらまめ通信 最新号 Vol.128のご紹介
- 2024年02月28日 お知らせ
-
2月に病院検索に加わった病院
- 2024年01月24日 セミナー
-
第35回 腎臓病を考える 都民の集い
- 2024年01月24日 セミナー
-
第5回 世界腎臓デーin鎌倉
- 2024年01月24日 セミナー
-
区民公開講座 あなたの腎臓と命を守るための治療について
- 2024年01月17日 そらまめ通信
-
そらまめ通信 最新号 Vol.127のご紹介
- 2024年01月05日 お知らせ
-
令和6年能登半島地震へのお見舞い
- 2023年12月27日 お知らせ
-
年末のご挨拶
- 2023年12月20日 お知らせ
-
12月に病院検索に加わった病院
- 2023年12月12日 お知らせ
-
「臓器取引と移植ツーリズムに関する動画」をご視聴ください


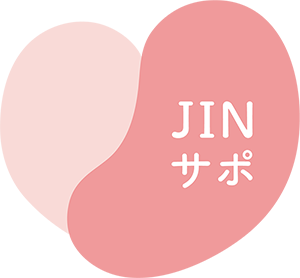






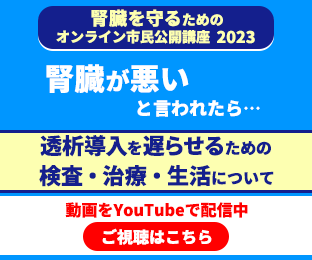
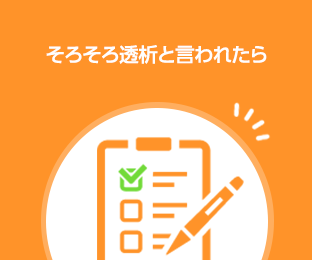
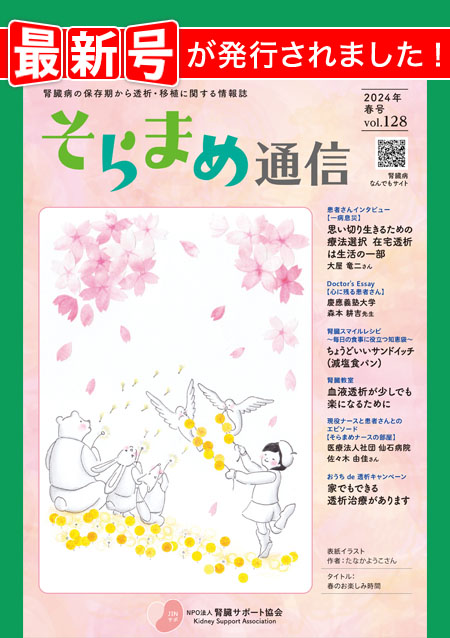

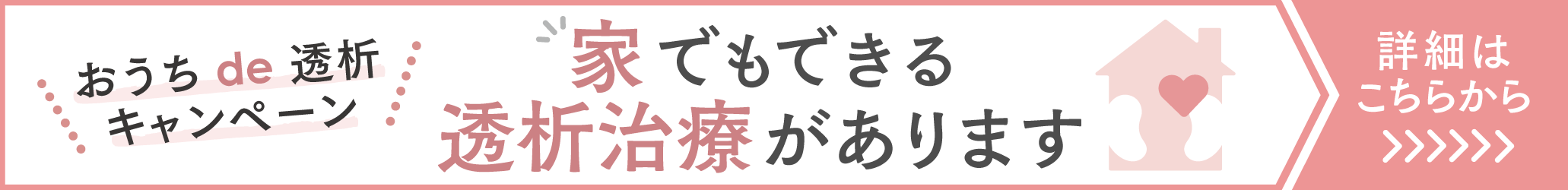
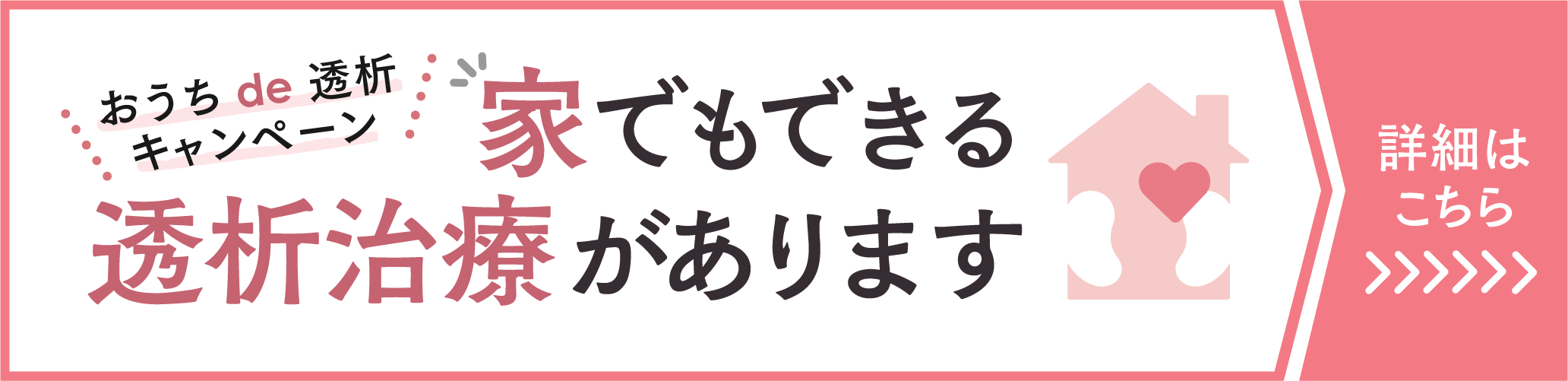







 腎臓サポート協会が
腎臓サポート協会が