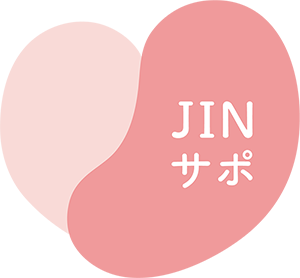心に残る患者さん ~ドクターズエッセイ~Vol.134(2025年10月号)
(先生の肩書は掲載当時のものです)

槇野 博史 先生 (まきの ひろふみ)
岡山大学前学長
香川県病院事業管理者
患者さんからの贈り物
1975年に岡山大学の医学部を卒業し、免疫とネフローゼに興味を持って大藤眞先生が主催される岡山大学第三内科に入局した。第三内科には全身性エリテマトーデス(SLE)をはじめ膠原病の患者さんが中国・四国地方の病院から紹介入院されていた。私の心に残っているのは臨床研修が始まり最初に“人工腎臓室”で出会った患者さんである。
20歳代の女性のループス腎炎(SLEによる腎障害)の患者さんで、澄んだ瞳が印象的だった。しんどそうであったが、研修医の私にも快く対応してくださった。関節痛と不明熱が持続していた。いくつかの病院では診断がつかず、大学病院に紹介された時には、既に腎機能は低下していた。副腎皮質ホルモン大量療法で腸管出血を起こしたために、副腎皮質ホルモンを減量して免疫抑制剤を併用したが、腎不全は進行して血液透析導入となった。その後、血圧を上昇させるレニンという物質が腎臓から分泌され、血圧が上昇し、降圧薬でもコントロールできず、重篤な心不全に陥った。両側の腎臓摘出により、血圧が安定して、心不全も軽快し、SLEの活動性は低下した。その後、前向きなその患者さんは、腎移植を受けられ、経過は順調であったが、合併症でお亡くなりになったと聞いた。
1970年代は血液透析と腎移植の黎明期で、この患者さんは第三内科で最初の透析導入の患者さんであった。当時はSLEそのものがよく知られておらず、この患者さんのように大学病院に紹介されてきた時には腎障害が進行し、ネフローゼ症候群や腎不全を合併されていた方も少なくなかった。この患者さんとの出会いにより、ループス腎炎の早期診断と治療により、透析にならないようにすることが私の研究テーマとなった。さらに腎臓と血圧の関係についても、この患者さんから大きな示唆を頂き、その後の降圧薬の腎保護作用の臨床研究に繋がった。
ループス腎炎の診断のためには腎生検による病理診断が必要である。カルテ庫に何日も籠って、第三内科のこれまでのループス腎炎の患者さんの入院カルテと腎生検病理組織標本を集めた。100例以上に及んでいたが、先輩に腎病理診断を教えて頂き、後輩にも手伝って貰って、臨床症状と病理組織学的な関係と治療による臨床所見と組織変化などを明らかにできた。
2001年にはニューヨークのコロンビア大学でのループス腎炎の病理診断基準改訂の国際委員会に我が国を代表して出席する機会を頂いた。改訂の日本案を会議の直前に提出するなどして、改訂に貢献することができた。この時の分類法はグローバルスタンダードとして現在でも活用されている。日本の腎臓学会では、日本中どこでも安全に腎生検をおこない、しっかりとした病理診断ができるようにと、腎生検病理診断標準化委員会の長を拝命し、指針を作成して普及することができた。この患者さんが原点となって、その後も国内外問わず、慢性腎臓病対策に関わることができた。改めてこの患者さんから頂いた贈り物のありがたさをかみしめている日々である。